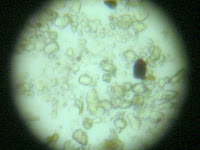エビガライチゴ(Rubus phoenicolasius)

 冬芽が育った小枝は約20cm。先端に数個の蕾の集合を着ける。
冬芽が育った小枝は約20cm。先端に数個の蕾の集合を着ける。
 新しいシュートも40cmほどに育っている。
新しいシュートも40cmほどに育っている。全体に赤い毛、赤い棘が多いが、シュートの中ほど以下では意外と白っぽい。
カジイチゴ(R. trifidus)

 カジイチゴは2月10日にもう咲き出した。先走った花は、左のように雌蕊不良のものが多い。右はもっこりと雌蕊が付いている正常花。本格的に咲き出すのは3月に入ってから。
カジイチゴは2月10日にもう咲き出した。先走った花は、左のように雌蕊不良のものが多い。右はもっこりと雌蕊が付いている正常花。本格的に咲き出すのは3月に入ってから。他の種でも、元気が悪いと雌蕊が無いことがよくある。カジイチゴやクサイチゴは、雄蕊が全開になるため判りやすい。
撮影は3月13日。


 現在のカジイチゴ。まだ咲き続け、実を太らせている。ひとつだけ熟したものも見られた。露地植えにすると、放置でもどんどん大きくなる。シュートはすでに人の背丈クラス。太いものは基部直径が2cmにもなる。
現在のカジイチゴ。まだ咲き続け、実を太らせている。ひとつだけ熟したものも見られた。露地植えにすると、放置でもどんどん大きくなる。シュートはすでに人の背丈クラス。太いものは基部直径が2cmにもなる。
クサイチゴ(R. hirsutus)
 4月11日撮影。裏庭に勝手に生えているもの。
4月11日撮影。裏庭に勝手に生えているもの。クマイチゴ(R. crataegifolius)

 4月11日開花。花弁が小さく、萼が目立つ花。数cmの小枝の先に数花集めて着ける。
4月11日開花。花弁が小さく、萼が目立つ花。数cmの小枝の先に数花集めて着ける。 現在の若実。熟すのは下旬ごろか。
現在の若実。熟すのは下旬ごろか。 シュートは現在30cmほど。黒い鋭い棘、緑地に赤い斑点、何度見ても極悪人面。
シュートは現在30cmほど。黒い鋭い棘、緑地に赤い斑点、何度見ても極悪人面。コジキイチゴ(R. sumatranus)

 コジキイチゴは、バラの鉢の実生が2年目を迎えたところで、今年の花は無し。シュートは30cmあまり。
コジキイチゴは、バラの鉢の実生が2年目を迎えたところで、今年の花は無し。シュートは30cmあまり。クマイチゴに劣らず棘がきつい。ただこちらは、他の植物にしな垂れかかるため、という理由も兼ねる。
ナワシロイチゴ(R. parvifolius)



 小枝は20cm前後、その先に蕾を集める。シュートは60cm。薄い産毛にしっかりした棘。葉裏は毛が密生して白。
小枝は20cm前後、その先に蕾を集める。シュートは60cm。薄い産毛にしっかりした棘。葉裏は毛が密生して白。ニガイチゴ(R. microphyllus)

 3月27日開花。撮影は4月6日。
3月27日開花。撮影は4月6日。
 現在は、授粉した若実が萼をつぼめている状態。ナワシロ、エビガラ、フユなどでも見られる特徴。シュートは50cm。
現在は、授粉した若実が萼をつぼめている状態。ナワシロ、エビガラ、フユなどでも見られる特徴。シュートは50cm。バライチゴ(R. illecebrosus)
 植え替えを検討したが、基部を確認したところ、冬芽は残っているようだったので、そのまま様子を見た。その芽が育って、こんもりするまでに復活してきた。なんとか来春には間に合わせたい。
植え替えを検討したが、基部を確認したところ、冬芽は残っているようだったので、そのまま様子を見た。その芽が育って、こんもりするまでに復活してきた。なんとか来春には間に合わせたい。
ヒメバライチゴ(R. minusculus)


 3月24日開花。4月6日撮影。
3月24日開花。4月6日撮影。小振りな姿ながら大量の蕾が着いた。花はクサイチゴに酷似。
湖西市で初見、採取したが、愛知県民の森にもたくさん生えていた。
 現在の様子。かなり歯抜けで受粉がうまくいってない。モミジイチゴはうまくいっているので、虫がいないということはない。採取したのが一株だったせいか。
現在の様子。かなり歯抜けで受粉がうまくいってない。モミジイチゴはうまくいっているので、虫がいないということはない。採取したのが一株だったせいか。フユイチゴ(R. buergeri)
鉢置き場の下草になっているフユイチゴ。新芽が盛大に伸び、鉢より這いあがらんばかり。
モミジイチゴ(R. palmatus)


 3月13日キレハ株が開花。丸弁株、細弁株より数日早い。
3月13日キレハ株が開花。丸弁株、細弁株より数日早い。19日撮影。キレハ株は八分咲きといったところ。

 同日、丸弁株と細弁株。
同日、丸弁株と細弁株。 キレハ株の現在。順調に育っている。いずれの株も、ずっと実が着かなかったが、すこしばかり肥培するだけで毎年たわわに生るようになった。
キレハ株の現在。順調に育っている。いずれの株も、ずっと実が着かなかったが、すこしばかり肥培するだけで毎年たわわに生るようになった。雑種:カジコジキ(R. trifidus × R.sumatranus ※※)
コジキカジと変わらないが、成長は悪い。20cmに満たない状態。
雑種:コジキカジ(R. sumatranus × R.trifidus ※※)



 花は咲かなかった。シュートは元気よく50cm。毛や棘は、コジキとカジの中間的。
花は咲かなかった。シュートは元気よく50cm。毛や棘は、コジキとカジの中間的。3出複葉が基本で、それぞれが割れる形の葉。頂葉はほぼ3裂しており、側葉が2裂しつつある。ブラックベリー系で見られる形に似る。
雑種:カジモミジ(R. trifidus × R.palmatus ※※)

 5株のうちの2号株。4号、5号もほぼ同じ特徴。なお1号はヒメカジイチゴに分類。
5株のうちの2号株。4号、5号もほぼ同じ特徴。なお1号はヒメカジイチゴに分類。オオモミジイチゴと呼びたいような芽や葉。やや掌状気味になってカジに近くなっている葉も見られる。毛はなく棘はまばら。シュートは現在60cm。
頑強さは劣り、特に前年枝は自立ができるかどうかのギリギリの状態。雨に打たれれば枝垂れてしまう。
花は咲かなかった。

 5株のうちの3号株。著しく小葉のもの。
5株のうちの3号株。著しく小葉のもの。冬芽はしっかりしていたが、花は咲かなかった。こんもりと茂った状態。シュートも5cmほどのものが出ている。葉の色は濃い緑、茎は赤。棘はあったりなかったり。毛はない。
雑種:トヨラクサイチゴ(R. × toyorensis)


 根詰まってきたトヨラクサイチゴ。4月6日開花。11日撮影。蕾のみ6日撮影。
根詰まってきたトヨラクサイチゴ。4月6日開花。11日撮影。蕾のみ6日撮影。花だけでは、クサイチゴやヒメバライチゴとの区別は難しい。

 わずかに採れたた種からの実生に、元気なシュートが出てきた。現在50cmほど。親に似て変化に富む。
わずかに採れたた種からの実生に、元気なシュートが出てきた。現在50cmほど。親に似て変化に富む。雑種:ヒメカジイチゴ(R. × medius)
カジモミジ1号株は、明らかにヒメカジイチゴの特徴なのでここに移設。


 2月28日、冬芽から蕾が覗く。3月14日、蕾成長。19日開花。直径3cm。
2月28日、冬芽から蕾が覗く。3月14日、蕾成長。19日開花。直径3cm。

 4月6日の様子。最後のみ現在の様子。
4月6日の様子。最後のみ現在の様子。授粉した若実はつぼむ。ニガイチゴの血によると思われる。

 4月初旬から、ヒメカジイチゴの実生にも花が咲いた。去年と同様に花弁先端が割れている。環境ではなく、株の持つ特徴のよう。花粉親が誰かは不明。花弁の割れるブラックベリー系とは花期が違う。モミジ、ニガ、クサ、カジ、クマ、トヨラクサ、コジキ、ボイセンの可能性がある。ヒメバラも一致するが、採種当時には手許になかった。
4月初旬から、ヒメカジイチゴの実生にも花が咲いた。去年と同様に花弁先端が割れている。環境ではなく、株の持つ特徴のよう。花粉親が誰かは不明。花弁の割れるブラックベリー系とは花期が違う。モミジ、ニガ、クサ、カジ、クマ、トヨラクサ、コジキ、ボイセンの可能性がある。ヒメバラも一致するが、採種当時には手許になかった。現在シュートが50cm。茎葉の様子はニガイチゴそのもの。
ブラックベリー・エバーグリーン(R. laciniatus ※)
前年の葉がわずかに残り、冬芽がようやく動き出したところ。現在5cmほど。
ブラックベリー・ソーンフリー(R. fruticosus ※)



 ブラックベリー系は目覚めが遅い。最近になってやっと動き出した。
ブラックベリー系は目覚めが遅い。最近になってやっと動き出した。小枝は10cmほど、頂部に複数、脇にひとつずつ蕾を着けている。
ボイセンベリー(R. ursinus × R.idaeus ※)


 ボイセンベリーがちょうど開花。小枝を15cmほど伸ばし、先端に1~3花まとめて着ける。蕾は不器用に丸めた形。直径1cmほど。シュートは現在30cm。
ボイセンベリーがちょうど開花。小枝を15cmほど伸ばし、先端に1~3花まとめて着ける。蕾は不器用に丸めた形。直径1cmほど。シュートは現在30cm。半数ほどが虫害に遭う。バラの蕾が全滅しており、バラゾウムシではないかと想像。
ラズベリー・インディアンサマー(R. idaeus ※)
 間違って切ってしまった前年枝の根元にあった芽が、20cmまで伸びてきた。この調子なら秋果は間違いなさそう。
間違って切ってしまった前年枝の根元にあった芽が、20cmまで伸びてきた。この調子なら秋果は間違いなさそう。ラズベリー・ファールゴールド(R. idaeus ※)
 どうしても夏以降調子を落とすファールゴールド。植え替えをしたら、小苗ばかり大量にできてしまった。とりあえず数本をまとめ植え。根の大きさを考えれば、今のところ順調といえそう。
どうしても夏以降調子を落とすファールゴールド。植え替えをしたら、小苗ばかり大量にできてしまった。とりあえず数本をまとめ植え。根の大きさを考えれば、今のところ順調といえそう。学名出典:
無印……YList
※……Wikipedia キイチゴ属
※※……文献無し