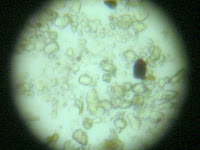キイチゴたちもすっかり冬支度。冬芽を確保し葉を落とし、空っ風に耐える準備をしている。
……などと書く気でいたものの、年を越してしまい、一部では春を迎える動きすら見えてきている。
エビガライチゴ(
Rubus phoenicolasius)

エビガライチゴはかなり長く伸びるので、支柱を渡る螺旋状にしてみた。
すでに葉は落ちた。一部は葉柄を残す独特の落葉の仕方をしている。真っ赤だった毛も、すっかり色あせた。

冬芽はそれほど大きくない。うっすら産毛を生やす。葉柄を残して落葉するのは、この冬芽を保護する意味があるのかもしれない。
カジイチゴ(
R. trifidus)

カジイチゴは節操がない。
前年の葉をまだ着けるもの、落葉したもの、小指の先ほどもある冬芽を膨らませるもの、蕾まで出してしまうもの……さすがに蕾はこれひとつだったが、おそらくこれは2月中には咲き、全体としては6月頃まで実を着けながら咲き続けると思われる。

虫害を受けたらしい枝があった。植物食性のハチか何かか。
もう少し経って芽吹きの季節になると、新芽の葉を綴って中を食い荒らす毛虫が大量発生する。膨らみかけたまま、いつまでも葉を展開しない新芽が多くなり、手で開いてみると1~数匹の毛虫が巣食っている。人に害のある虫ではないものの、せっかくの芽吹き、開花が見られなくなってしまうのは勘弁。
クサイチゴ(
R. hirsutus)

家の裏に勝手に生えたもの。
日があまり当たらない場所なので、育ちは悪い。風も当たらないため、紅葉も落葉もほとんどない。

冬芽は少し芽吹きかけたようになっている。
クマイチゴ(
R. crataegifolius)

すっかり落葉し、産毛の生えた冬芽で冬を越す。先端が丸っこい。
あまり大きくないのは、鉢植えで育ちが良くないせいかもしれない。
コジキイチゴ(
R. sumatranus)

コジキイチゴは、鉢植えはとうに枯れ、そこから逃げた庭植えも昨夏枯れてしまった。手持ちの株がなくなってしまった、と思っていた矢先、バラの鉢にキイチゴらしい芽吹きを確認。そのまま育ててみたところ、コジキイチゴだったようだ。おそらく、庭の実りをついばみに来た者が、置き土産をしていったんだろう。
2株ほど生えている。樹高は15cm程度。
ナワシロイチゴ(
R. parvifolius)

ナワシロイチゴは庭先の土手などに自然発生している。
まだ黄葉がわずかに残る。

幹も細いが、冬芽もかなり小さい。
ニガイチゴ(
R. microphyllus)

すっかり落葉している。トレードマークの「粉を吹いたような」幹と小さめな冬芽が見える。ここから2~3葉出した後に蕾を着ける。
棘はやや上向きにカールする。
バライチゴ(
R. illecebrosus)

一昨秋、麻生山で採種したバライチゴ。いままで旺盛だったのが、この秋冬あたりで急に衰えてしまった。冬芽をつくるどころか幹が萎れて、先端からどんどん枯れこんできた。現在は地際3cmほど生きているかどうか、の状態。原因は不明。バラで被害を受けた、コガネムシの幼虫にでも入られたのかもしれない。根を確認してみようか検討中。
ヒメバライチゴ(
R. minusculus)

昨夏、湖西市で採取したもの。樹高はたいしたことはないが、冬芽は立派。開花が望めそう。
フユイチゴ(
R. buergeri)

鉢から脱走し、鉢置き場の下草になっているフユイチゴ。10月初め頃から熟し始め、盛りになった11月初旬の写真。年を越えるまで実りの季節は続く。
モミジイチゴ(
R. palmatus)

魚の骨のような葉を持つキレハ株。冬芽はしっかり育っている。

花弁の細長い細弁株。全体に細く、よく枝垂れる。冬芽は小ぶりで細長い。
どこから迷い込んできたのか、シロバナシランが発生。大繁殖し鉢内を圧迫していたので、やむなく植え替え整理をした。

花弁の丸い丸弁株。非常に直立性。がっしりして幹も太め。冬芽もよく育っている。
雑種:カジコジキ(
R. trifidus ×
R.sumatranus ※※)

カジイチゴを母に、コジキイチゴを父にした雑種。両親の形質を受け継いでいる。コジキカジに似る。

棘に関しては、コジキイチゴを受け継ぐ。
雑種:コジキカジ(
R. sumatranus ×
R.trifidus ※※)

コジキイチゴを母に、カジイチゴを父にした雑種。両親の形質を受け継ぎ、カジコジキによく似る。カジコジキより育ちがいいかもしれない。

やはり棘が鋭く、赤く毛深い。

3出の頂葉が3裂もしくは3小葉化し、側葉は基部側に2裂もしくは2小葉化する。

葉表には艶がある。

葉裏は薄緑色地に赤い葉脈、脈上には赤い毛が多い。
雑種:カジモミジ(
R. trifidus ×
R.palmatus ※※)

カジイチゴを母に、モミジイチゴを父にした株。
ただしこの株に限っては、あらゆる特徴がヒメカジイチゴであり、近くにニガイチゴの株もあることから、偶然発生したヒメカジイチゴと思われる。棘はほとんどなく、成長がよく、冬芽も大きい。

標準的と思われる株の冬芽。これもよく育っている。棘はある。

標準株は、きれいに紅葉し、まだ一部が残る。

この矮小株も、同じ実から生えた株。樹高は10cm強しかない。葉は500円玉程度。

矮小株の冬芽は、ほかに比べるとやや小ぶりだが、樹高などとの比を考えれば大きい。かなり寸詰まりに見える。
雑種:トヨラクサイチゴ(
R. ×
toyorensis)

クサイチゴとカジイチゴの雑種とされる。
植えっぱなしで調子の上がらない株。クサイチゴの血か、冬芽が冬芽然としていない。少しほころびかけて留まっているものが多い。

トヨラクサイチゴは、結実しにくい。授粉しても、キイチゴ状果には遠く及ばない歯抜けになる。そんな中から種子を取り出し播種。発芽率も良くない中から生き延びた、トヨラクサイチゴの実生株。
いい加減に世話をしていたせいか、まだ大きくならない。大鉢に移してから大きな葉が出るようになった。トヨラクサイチゴとして生を受けているなら、春には7小葉が出るかもしれない。

トヨラクサイチゴ実生株の、葉表には細かい毛が多い。斜めから光を当ててみるとよく判る。
雑種:ヒメカジイチゴ(
R. ×
medius)
もともとの株は調子を落としてしまった。カジモミジに1株、この種に該当すると思われるものが出ている。
ブラックベリー・エバーグリーン(
R. laciniatus ※)

昨秋咲いて実りかけた残骸とともに、まだ紅葉を残す。
根が詰まったか、成長がかなり収まった。植えた当初は、8号鉢ながら5mも伸びるという、驚きを超えて迷惑な成長ぶりだったので、植え替えはためらわれる。

成長振りを考えると控えめな冬芽。ただし棘は、根元へ向かってカールした鋭く大きなものを多数持つ。
ブラックベリー・ソーンフリー(
R. fruticosus ※)

支柱を立て、螺旋状に巻き上げてみた。
オレンジ色の葉を少し残す。

やや毛深い、先の尖った三角形の冬芽を持つ。
ボイセンベリー(
R. ursinus ×
R.idaeus ※)

巻くほど伸びていないが、螺旋風に巻いている。多少葉が残る。

ボイセンベリーの冬芽。
ラズベリー・インディアンサマー(
R. idaeus ※)

インディアンサマーの冬芽。新しいシュートと言うべきかもしれない。
植え替え時に、落ち葉に埋もれていた部分が表に出たもの。間違って切ってしまった前年枝のその根元の芽。
ラズベリー・ファールゴールド(
R. idaeus ※)

調子が良くないので、これも植え替えをした。20cm程度の小株が多数でき、そこにあった冬芽。

新シュートとなるこの芽は、植え替えで表土上に出てしまったのかもしれない。
学名出典:
無印……
YList
※……Wikipedia
キイチゴ属
※※……文献無し